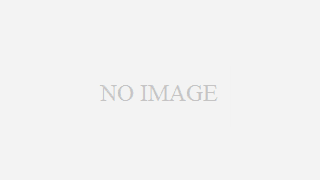 鶏胸肉を使った料理
鶏胸肉を使った料理 鶏胸肉と野菜の甘酢炒め
中華風鶏胸肉の甘酢あんかけ:疲れて食欲がないときでも優しい甘酸っぱさで無理せずごはんがすすみます。健康を意識して高蛋白質の鶏胸肉を使っていますが、豚肉を使えばコッテリとした若者向けの一皿に変わります。
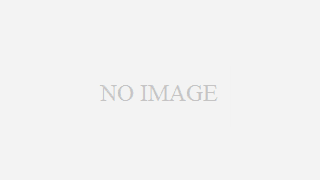 鶏胸肉を使った料理
鶏胸肉を使った料理 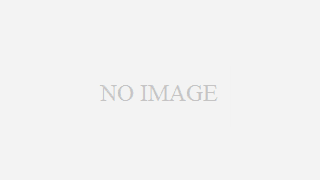 鶏胸肉を使った料理
鶏胸肉を使った料理 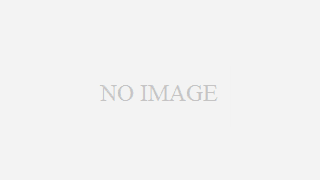 豚肉を使った料理
豚肉を使った料理 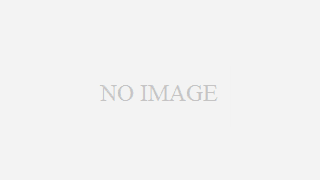 鶏胸肉を使った料理
鶏胸肉を使った料理 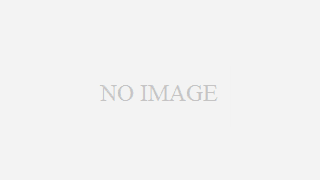 鶏胸肉を使った料理
鶏胸肉を使った料理 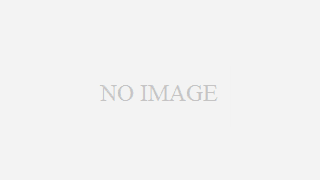 鶏胸肉を使った料理
鶏胸肉を使った料理 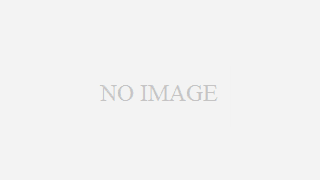 中国
中国 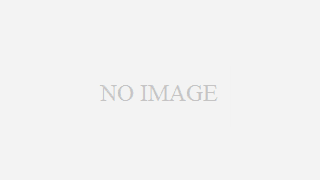 中国
中国 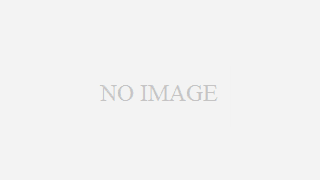 韓国
韓国 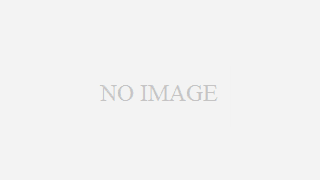 中国
中国